
「お薬」は国から承認を受けなければ医療機関や薬局で取り扱う事ができません。
国から「お薬」として承認を受けるために、さまざまな試験を繰り返し、効き目と安全性の評価が行われますが、 最後の段階で健康な人や患者さんのご協力を得て行われる試験を「治験」といいます。
人における試験を一般に「臨床試験」と言いますが、「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験が、 特に「治験」と呼ばれ、「くすりの候補」が「治験薬」と呼ばれています。
今私たちが使っている「お薬」は、多くの患者さんのご協力による「治験」を経て誕生したものです。
国から「お薬」として承認を受けるために、さまざまな試験を繰り返し、効き目と安全性の評価が行われますが、 最後の段階で健康な人や患者さんのご協力を得て行われる試験を「治験」といいます。
人における試験を一般に「臨床試験」と言いますが、「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験が、 特に「治験」と呼ばれ、「くすりの候補」が「治験薬」と呼ばれています。
今私たちが使っている「お薬」は、多くの患者さんのご協力による「治験」を経て誕生したものです。
「治験」を実施しています。
治験では、
治験では、
- 治験担当医師による最新の薬物治療が提供されます。
- 治験協力者である医療スタッフが被験者のサポートを致します。
- 看護師による細心の看護が提供されます。
- 薬剤師による説明、副作用管理がされます。
- 検査技師・放射線技師による厳正な検査が行われます。
- 医事課職員により被験者の不利益が回避されます。
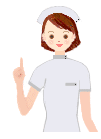
治験は国際基準にのっとり厚生労働省が定めたGCP(Good Clinical Practice)という基準に従って厳格に行われます。
1.治験審査委員会での審議
院内に治験審査委員会(月に1回開催)を設けて、実施する治験の内容が妥当なものであるかが審議されます。
委員には医学・薬学の専門家に加え、非専門家および院外の有識者にも加わっていただき被験者の人権が大切にされているか検討されます。
2.自由参加と同意の取得
治験に参加するかどうかは、参加される方の自由意志で決まります。
治験への参加を強制されることはありませんし、参加を断っても何ら不利なことはありません。
治験参加にあたっては、十分な説明を受けたうえで、文書で同意を取ることになっていますが、同意しても、いつでも、どんな理由でも参加を取りやめることができます。
3.プライバシー
治験では、被験者のデータを依頼者である製薬会社や厚生労働省の担当者が閲覧することになりますが、プライバシーは保護されます。
院内に治験審査委員会(月に1回開催)を設けて、実施する治験の内容が妥当なものであるかが審議されます。
委員には医学・薬学の専門家に加え、非専門家および院外の有識者にも加わっていただき被験者の人権が大切にされているか検討されます。
2.自由参加と同意の取得
治験に参加するかどうかは、参加される方の自由意志で決まります。
治験への参加を強制されることはありませんし、参加を断っても何ら不利なことはありません。
治験参加にあたっては、十分な説明を受けたうえで、文書で同意を取ることになっていますが、同意しても、いつでも、どんな理由でも参加を取りやめることができます。
3.プライバシー
治験では、被験者のデータを依頼者である製薬会社や厚生労働省の担当者が閲覧することになりますが、プライバシーは保護されます。
- (1)新しい薬物治療をいち早く受けることができます。
- (2)専門の治験担当医師が一貫して診察にあたります。
- (3)通常の治療より詳しい検査や診察を行います。
- (4)通常の受診の際はもちろん、好ましくない症状が出た場合など、常に治験コーディネーター(CRCともいいます)と呼ばれる看護師と薬剤師が被験者をサポートします。
- (5)通院にかかる負担を軽減する目的で一定の範囲で、通院のための交通費等、負担軽減費が支払われます。
- (6)同じ病気で苦しむ人のためによいお薬を残すために協力するという社会貢献ができます。
- (1)治験薬の効果や安全性を確認するために、通常の診療より来院回数や検査が増えることがあります。
- (2)治験薬では、今までに報告されていない副作用がおこる可能性があります。
- (3)正確な服薬や治験のスケジュールにそった来院だけでなく、患者日誌の記録など様々な協力をお願いすることがあります。
- (4)治験は決められた病院でしか行うことができません。他の病院に行かれる時は治験担当医師に相談していただく必要があります。市販のお薬を使う場合も相談が必要です。