チーム医療
摂食嚥下(せっしょくえんげ)
「摂食」とは人として基本的な行為である「食べること」を指し、「嚥下」とは摂食時の飲み込む行為であり、食物を口腔より胃に送り込むことです。
本来であれば、口から食道に到達すべき水分や食物が気管から肺に入り、食物を口から安全に食べられない状態を「摂食嚥下障害」といいます。
チームの特色
「摂食嚥下チーム」では、栄養状態、食事の状態、口の中の衛生状態を確認・評価し、多くの医療専門職 (医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、管理栄養士、薬剤師) との連携により治療や訓練をすることで、食べる機能の回復や肺炎を防止し、適切な栄養状態の維持を図っています。 患者の『食』をサポートするためにさまざまな役割を果たしているのが「摂食嚥下チーム」です。
診療する主な病気(病名)
- 嚥下機能が低下している患者さん
原因には、脳卒中や神経変性疾患、加齢に伴うもの、心因性によるものなどがあります。全肺炎患者の約4分の1が誤嚥性肺炎といわれています。 高齢者は、咀しゃく力の低下、嚥下筋の筋力低下、味覚の低下、注意・集中力の低下等を要因として嚥下機能が低下し、 また、免疫力の低下により、わずかな誤嚥が重篤な肺炎を引き起こす可能性があります。 - 誤嚥(ごえん)
食物や唾液が気管から肺の方へ侵入する現象をいいます。一般的にお茶などを飲んだときにむせることがありますが、 「むせる」ことは、気管に入りかかった空気以外の異物を排出しようとする生体の防御反応です。 しかし、気道の感覚が低下していると誤嚥していてもむせないことがあります。 脳卒中を起こした方は、生体の防御機構や抵抗力の低下により、誤嚥性肺炎の危険性が高くなります。 (「誤飲」とは乳幼児に多く、食品以外のもの(ボタンや小銭など)を 誤って飲み込んでしまうことをいい、「誤嚥(ごえん)」と区別しています)
主な活動

嚥下回診
嚥下回診では、摂食嚥下障害のある患者さんの状態を把握し、摂食嚥下機能の評価を行い、 口から美味しく食べるためのリハビリテーションの内容や食事時の姿勢や食事形態の調整などについて検討しています。

口腔ケアラウンド
義歯の不具合、歯牙の欠損など、お口のトラブルに対して歯科医師・歯科衛生士・看護師か らなる口腔ケアチームが回診しお口の中の衛生に努めています。

嚥下評価
摂食嚥下障害が疑われる患者さんに対して嚥下内視鏡検査や嚥下造影検査を行っています。 検査では患者さんが実際に食べているものを用いて、のどの動きや食物の流れを詳しく評価し 患者さんの飲み込みの状態を確認しています。


教育
患者さんが安全に口から食べられるように食事姿勢や食事介助方法、誤嚥対策などの研修を開催しています。




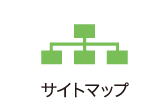


 外来担当一覧(PDF)
外来担当一覧(PDF)