チーム医療
DMAT(ディーマット)
Disaster Medical Assistance Team の頭文字をとった災害派遣医療チームの略称です。 医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職及び事務職員)を基本とする4~5名で編成され、大規模な災害や事故現場、テロなどの緊急事態に迅速に対応するための医療チームです。 当院には2025年1月現在、医師5名、看護師7名、業務調整員6名(事務職員、臨床工学技士、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士)の計18名が在籍しています。
発足のきっかけ
1995年1月17日に起きた「阪神・淡路大震災」では、災害時における医療体制が十分に整えられていませんでした。この地震で被災された方のうち、いつも通りの救急医療が提供されていれば、救命できたと考えられるいわゆる「避けられた災害死」が500名あまりにのぼると報告されています。 この震災での医療対応の課題や教訓が、日本における災害医療体制の強化と専門的な医療チームの必要性を浮き彫りにし、2005年4月日本DMATが誕生しました。
災害拠点病院
当院は、砺波医療圏(砺波市、小矢部市、南砺市)で唯一の災害拠点病院に指定されています。
災害発生時にはDMATを中心に、まず自院および砺波広域圏を守る体制を整え、地域の皆さんを守る最後の砦としての役割を担います。
そのため、毎年1回、緊急時に全職員が迅速に行動できるよう、災害をシミュレーションした訓練を実施しています。
砺波DMATの活動【令和6年能登半島地震】
当院では国からの派遣要請を受けDMATを3隊石川県に派遣しました。また、陸上自衛隊富山駐屯地(砺波市)の施設内にて被災地から搬送された患者、施設利用者を県西部の病院に分散搬送する任務をサポートしました。
1次隊 派遣期間:1月2日(火)~1月4日(木) 派遣場所:町立富来病院
発災2日目、この日は奥能登に位置する珠洲・輪島へのルートがまだ確立されていなかったため、志賀町の町立富来病院に派遣されました。志賀町も震度7を観測した地域であり、富来病院は今回の地震で最も建物被害が大きかった病院の一つでした。11時に当院を出発し、悪路を約5時間進んだ後、現地に到着し活動を開始しました。
富来病院では約70名の入院患者がいたものの、建物の損壊や漏水が発生し、特に2階の被害が甚大で、診療継続が困難な状況でした。
そんな中、私たちに与えられたミッションは、搬送計画の立案と実施、そしてそれまでの診療継続のサポートの2つでした。
活動中、看護師は主に夜勤の支援を担当し、医師や業務調整員は搬送計画の立案、物資整理、病院スタッフとのミーティングや掃除作業などに従事しました。4日(木)の正午に現地を撤収し、その後引き継いだ後続のDMAT隊によって、5日(金)中に全患者の避難が完了しました。その後の建物診断では、病棟が立ち入り禁止と判定されたとのことです。
現地では電気は使用できたものの、断水しており、トイレは近くに貯水していた雨水やおむつを利用した簡易トイレを使用しました。食事は持参したご飯やレトルト食品を工夫して摂取しました。外来待合室の椅子の上で寝袋にくるまり就寝しましたが、余震のたびに目を覚ましました。
2次隊 派遣期間:1月5日(金)~1月7日(日) 派遣場所:公立宇出津総合病院
1次隊帰還後の翌日の発災5日目に能登に向かいました。5日目になると損壊していた国道が応急的に復旧されており、輪島や珠洲などの奥能登地域へのアクセスが可能となりました。そのため、私たちはDMATの支援が行き届いていなかった能登町にある公立宇出津総合病院に派遣されました。能登町へ向かう唯一の国道は復旧されてはいるものの、道路の亀裂や段差などが多く、道路脇に転落している車が放置されている状況であり、被害の甚大さを肌で感じました。
宇出津病院は外壁や一部の入院病棟の損壊はあるものの、診療継続は可能であり、救急患者の受け入れを行っていました。しかしながら、水道が復旧しておらず、手術や血液透析などを行うことが出来ないため、それらの治療が必要な患者は金沢の病院まで転院搬送が必要な状況でした。
さらに、病院の職員は発災からほとんど帰宅できておらず24時間働き詰めで疲弊していました。
そのため、私たちに与えられたミッションは、転院搬送な必要な患者の搬送計画の立案と実施、入院病棟や救急外来の支援でした。派遣2日目の午前には予定していた転院搬送が全て完了しましたが、先遣隊のDMAT2隊が撤収しなければならず、砺波DMAT1隊のみで活動を継続することとなりました。そのため、2日目の夜に追加派遣のDMAT3隊が到着するまで宇出津病院の支援の本部運営を引き継ぎ、チームで分担しながら、事務作業や入院病棟、救急外来の診療支援に従事しました。
3次隊 派遣期間:2月7日(水)~2月9日(金) 派遣場所:1.5次避難所
(いしかわ総合スポーツセンター)
発災後約1ヶ月が経過し災害急性期を過ぎた頃、被災地での支援活動はDMATから他の医療・福祉チームへ徐々に引き継ぎが行われていました。この方針は1月8日に金沢市内で開設された1.5次避難所(いしかわ総合スポーツセンター)でも同様であり、当院のDMAT第3隊目は1.5次避難所へ向かい、現地での撤退に向けた活動(業務整理や他の団体への申し送り等)の支援を行いました。
1.5次避難所は高齢者や障がい者等の要配慮者が、ホテル・仮設住宅等の2次避難所へ移るまでの期間を、被災地外の安全な場所で過ごすための一時的な受け入れ先として設けられ、電気・水道等のインフラは整っており支援者・支援物資も充実した環境でした。そのため医療ではなく福祉ニーズが高い状況でした。
第3隊目の具体的な活動としては二日間の夜勤業務を行い、夜勤帯の避難者対応や他職種からの相談対応、避難所管理マニュアルの修正や各種書類等の作成等を行いました。現地での活動では他団体への業務移行の難しさや、避難所生活が要配慮者に及ぼすストレスの大きさを痛感しました。支援者の撤退は避難者だけでなく他団体の支援者の不安を招く原因となる事から申し送りの際には言葉の使い方への注意や、分かりやすい資料の作成、十分な時間をかけて行う事等が徹底されました。
また避難者の中には不慣れな環境での生活から精神的に不安定になってしまい、問題行動を行ってしまう方も見受けられ、思いに寄り添ったきめ細やかなケアが求められました。
被災者の受け入れ 派遣期間:1月9日(火)、1月19日(金) 派遣場所:陸上自衛隊 富山駐屯地
この度の能登半島地震では、医療機関だけでなく高齢者福祉施設の被害も甚大となり被災状況に応じて入院患者、高齢者福祉施設入所者を金沢市内へ移送するという対応が連日のように行われていました。
石川県から富山県へは連日のように数十人規模での入所者受け入れ要請があり対応を行っていましたが、1月9日七尾市の高齢者福祉施設から自衛隊の救急車にて30名、1月19日には自衛隊ヘリ/消防防災ヘリにて11名を富山駐屯地で受入を行い呉西地区の医療機関への分散搬送が決定されました。
我々DMAT(医療)は毎年様々な災害を想定した訓練を行っていますが、今回のように富山駐屯地を使った訓練は行った実績はなく、正にぶっつけ本番での受け入れとなりました。
受け入れを行うにあたり幾つかの不安要素がありましたが、DMAT(医療)と消防、自衛隊の3つの機関が密な連携を取ったことで、スムーズにミッションを完遂することができました。



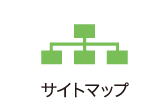


 外来担当一覧(PDF)
外来担当一覧(PDF)