診療科
救急部 集中治療・災害医療部
- 救急時間外案内図
(画像が開きます)
ICU・HCU案内図 (画像が開きます)
印刷用はこちら - 診療医紹介
- 科の特色
- 診察する主な病気(病名)
- 年間受付状況
- 重症度評価と予後予測
- 外傷データバンクレポート
- 砺波医療圏における救急(外傷)医療の状況
- DMAT
- 機器・設備

「携帯型迅速クレアチニン測定装置」が新規導入されました

(ノバ・バイオメディカル社)
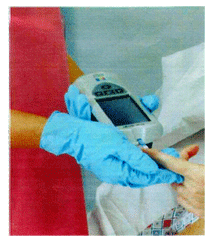
クレアチニンとは
臨床的に腎臓機能の評価に有用とされています。(基準値:0.4~0.8mg/dl)
迅速にクレアチニンが測定できるメリットは?
交通事故等により救急搬送された患者さんの中には、血管損傷や臓器損傷の有無を診断するために造影CT検査が必要となる場合があります。
〝造影〟とは、その名の通り、造影剤を投与して行いますが、その際に懸念されるのが「造影剤誘発性腎不全」など、造影剤が誘引となる腎機能障害です。
通常、採血(検体)を検査科に送り結果がでるまでに40分から1時間を要しますが、救急や緊急時ではその時間を待つことができません。
迅速にクレアチニン測定し、事前に腎機能を評価できれば、腎機能が低下している患者さんには造影剤投与量を調節することで合併症のリスクを軽減できると考え、
県内でいち早く導入しました。これにより、 医療スタッフは造影剤を用いた検査・治療が安心して行えると供に患者さんの安全性も向上します。
【CT画像】
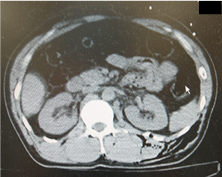
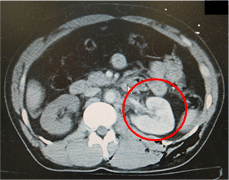
造影剤が流れる(血流がある)ところが白くなります。
造影CT上、左の腎臓(赤丸)は白く見えますが、反対側の腎臓は白くなっていない、
つまりは造影されていないため、腎臓への血流が途絶えていることが分かります。
【心臓カテーテル検査/治療】
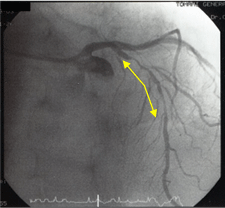
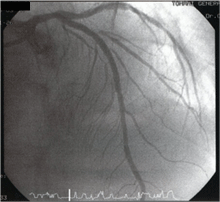
冠動脈の検査/治療は冠動脈に直接造影剤を投与しながら行われます。
〝治療前〟では矢印の範囲の血管が細くなっていますが〝治療後〟ではステントという金属の筒を植込んだことで血管径が保たれていることが分かります。
どんな時に使う?
【救急領域】
- 交通事故、転落等により搬送され血管損傷や臓器損傷の有無を診断するために造影CTが必要となる患者
- 心筋梗塞が疑われ緊急的心臓カテーテル治療が必要な患者
【放射線領域】
- 外来患者さんや紹介患者さんがCT検査を行う際、併せて造影CTも行う場合があります。 中にはクレアチニン検査がされていないケースもありますが、待ち時間を作ることなく対応できます。
【集中治療領域】
- 急性腎不全などにより血液透析、持続血液濾過透析を行っている場合、治療効率の評価ができます。



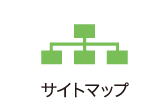


 外来担当一覧(PDF)
外来担当一覧(PDF)