診療科
整形外科
- 診察受付・診察時間
- 診療科までの案内図
(画像が開きます)
印刷用はこちら - 外来診療担当
- 診療医紹介
- 科の特色
- 診察する主な病気(病名)
- 年間治療(手術)状況
- 治療情報
- お知らせコーナー

髄腔内バクロフェン投与療法について
髄腔内バクロフェン投与療法について
市立砺波総合病院 整形外科 高木泰孝
バクロフェンは抑制性伝達物質のγ―アミノ酪酸(GABA)の誘導体で、代表的な中枢性筋弛緩薬です。 バクロフェンは脳血管関門の通過が困難で、経口では脊髄で十分な濃度にならず、重度の痙縮への効果は不十分です。
痙縮(けいしゅく)とは脳・脊髄の病気(例えば、脊髄損傷、脊髄小脳変性症、脳性麻痺、頭部外傷、脳卒中など)が原因で生じる 筋の異常な緊張のことで、筋肉が硬くなったり、こわばることをいいます。
痙縮のため普通に筋肉を伸ばすことができず、運動が障害されたり、長い期間続くと縮んで固まってしまうことがあります。 わずかな筋肉の刺激に反応して、筋肉が収縮してしまうようになります。「つっぱり」痛みを感じることがあります。 また程度が進むと持続性のこむら返りや貧乏揺すりのような動き(クローヌスといいます)が出てくることもあります。 足の痙性が増してくると、尖足(せんそく)といい、常につま先立ちしているような状態で足首の関節が固まってしまいます。 痙性が続くと、「拘縮(こうしゅく)」といい関節が固まってきてしまいます。
バクロフェンの家兎髄腔内投与で多シナプス反射の抑制が見出され、 ごく少量のバクロフェンを髄腔内投与するとヒト臨床試験で脊髄由来に対する効果が示されました。
米国Medtronic社は、薬剤を髄腔内に持続注入し、用量調整可能な埋め込み型ポンプを開発しました。 昭和59年にポンプを用いたバクロフェン髄腔内投与(髄腔内バクロフェン投与療法)の臨床試験が、脊髄損傷と多発性硬化症による重度の痙性麻痺患者で行われ、 ついで多施設共同臨床試験が実施されました。髄腔内バクロフェン投与療法の重度痙縮に対する著効が示され、長期間持続投与の安全性も確認され、 平成4年に脊髄性の痙縮に対してFDAで承認されました。その後、平成8年脳由来の重度痙性麻痺に対してFDAで承認されました。
以降欧米では12万例以上の髄腔内バクロフェン投与療法用のポンプが植込まれています。
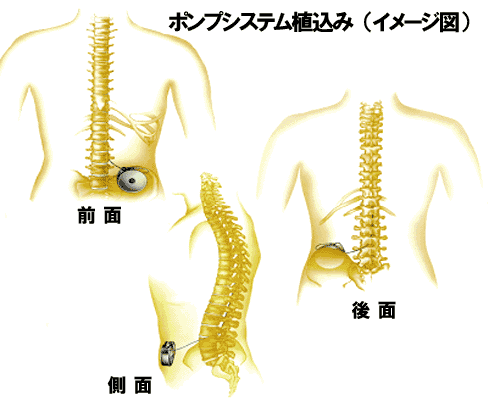
髄腔内バクロフェン投与療法では患者さん選択が最も重要です。他の治療が無効なことを確認し、 痙縮の程度、ADL(日常生活動作)への影響を評価して十分な説明の上で治療を行う必要があります。
ポンプを埋め込むかどうかは腰椎穿刺にて1回脊髄内に薬物を投与して効果判定を行うスクリーニング検査を予め行う必要があります。 効果を認めた患者さんに持続投与用のポンプを埋め込みます。手術は背部からのカテーテルを髄腔内に挿入して固定し、 腹部にポンプ留置のためのポケットを作成し、カテーテルを腹部に回し脳脊髄液の逆流を確認したのちにポンプとつなぎます。 電波式のプログラマーで体外から投与量を調整し、維持量を設定して退院となります。
その後、外来で調整を継続し、2~3ヶ月に1度薬剤を補充します。 ポンプの電池寿命は5~7年であり、ポンプを手術で交換して髄腔内バクロフェン投与療法を継続します。
我が国では25例の臨床試験が行われ有効性が確認され、2006年4月に健康保険での治療が可能となりました。 2023年10月末まで全国で約3,300例の植込み手術が行われています。治療を行う医師は、資格が必要です。 当院では整形外科 高木泰孝、リハビリテーション科 中波暁の2名の医師が資格を得ています。
当院では脊髄損傷など患者35名(2023年12月末)のポンプ植込みの経験があります。
当院では、整形外科・リハビリテーション科と協力して病院を挙げて、患者さんを治療する体制を整えています。



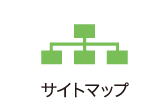


 外来担当一覧(PDF)
外来担当一覧(PDF)