看護部
専門・認定・特定看護師紹介
救急看護認定看護師 島 美貴子 皮膚・排泄ケア認定看護師 森田 初美 緩和ケア認定看護師 高島 留美 緩和ケア認定看護師 碓井 未央 がん化学療法看護認定看護師 山田 裕子 がん性疼痛認定看護師 前田 真裕美 感染管理認定看護師 村本 由子 感染管理認定看護師 高松 広彰 手術看護認定看護師 越塚 奈美 乳がん看護認定看護師 高畠 梨絵 摂食・嚥下障害看護認定看護師 田中 晴美 摂食・嚥下障害看護認定看護師 谷口 めぐみ 摂食・嚥下障害看護認定看護師 安田 賢治 認知症看護認定看護師 畑 真夕美 脳卒中看護認定看護師 池守 実智代 呼吸器疾患看護認定看護師 岸澤 由紀子 クリティカルケア認定看護師 森田 高彰 がん放射線療法看護看護師 臺蔵 由紀子

特定行為看護師 八田 枝美 特定看護師 鍋田 里子 特定看護師 大笹 里菜

|
がん看護専門看護師 師長代理 平 優子 |
私は、がん相談・肝疾患相談支援センターに所属し、院内外の「がん」「肝疾患」に関する相談を承っています。
がんと診断を受けてから、治療・人生の最終段階におけるまで、パートナーの一人として一緒に考えていきたいと思います。
|
がん看護専門看護師 師長代理 山田 裕子 |
私は、外来化学療法室における看護実践を活かしながら、がんの診断後から人生の終末における看護ケアを、 時期や場所を問わず、どなたでも受けていただくことができるように、多くの専門職と協働しています。
また、その人の中の健やかさに働きかけたり、本来備わっている力、自然治癒力が促進されるように、 こころとからだ、暮らしの視点からその人の全体性を捉え、がんと共に生きる療養環境の調整に関わっています。
|
老人看護専門看護師 師長代理 長瀬 佐知子 |
この地域に暮らす高齢者の方々が、認知機能や足腰の筋力が低下してこれまでと同じ暮らしの場に戻ることが簡単ではないと思われた時、
その方にとってどうすることが最善かをご家族と共に考えていきたいと思います。
また、人生で大切にしてきた価値観を思い出し、最期までその人らしい時間を過ごしながら望む生き方と逝き方にできるだけ近づけるよう、
関わらせていただきたいと思います。
病院スタッフが、医療という枠にとらわれずにご本人とご家族を尊重する姿勢を軸に関わることができるよう院内教育にも携わっていきます。
|
小児看護専門看護師 中田 史世 |
私は、小児看護専門看護師として、地域で暮らす子どもたちの健やかな成長・発達を支援すると共に、 慢性疾患・発達障害をもつ子どもたちや医療的ケア児とその家族が安心して生活できるよう相談、サービス調整、地域との連携などを行っています。
【相談内容】
・子どもの悩みや不安の傾聴、助言
・子育てに困っている親子への子育て支援、地域サービスの情報提供
・病気をもつ子どもとその家族に対する相談、サービス調整
様々な悩みを抱えながら成長する子どもたちやご家族の悩みに耳を傾け、心身の育ちを促す支援を行いながら、 子どもの成長をご家族と共に支えていきたいと考えています。
毎週水曜の午後、小児科外来において子どもと家族のための看護外来を行っています。相談されたいことがあれば、遠慮なく小児科外来へご連絡下さい。
|
救急看護認定看護師 科長 島 美貴子 |
みなさん、救急室を受診されたことはありますか。救急室は、急に始まった辛い症状に対し、緊急性と重症度を判断し、 救急医師とともに適切な時間に診療を始め、できるだけ早く辛い症状を緩和できるよう対応する場所のことをいいます。救急室では、 小さいお子さんから、高齢の方まで幅広い年齢層の方や、発熱やケガ、時には生命に関わる大きな病気など、24時間さまざまな症状の患者さんに対応しています。 そのため、救急看護師は、多くの知識や、緊急に対応できる技術が必要になります。
このように、救急看護は、日常生活の中で突然発生することと関連が多く、みなさんの生活と直接関係しています。 現在活動範囲は病院内ですが、今後は、どのような状態になったら救急受診すればいいのか家庭でも分かる救急看護の相談や、病院から退院するときに、 緊急時はどうすればいいのかが分かる緊急対応など、ご希望があれば詳しく説明をさせていただきます。皆さんが、安全で安心した日常生活を送ることが できるような相談もお受けしています。どうぞ、お気軽にご相談下さい。
|
皮膚・排泄ケア認定看護師 師長 森田 初美 |
皮膚・排泄ケアとは、創傷・ストーマ・失禁に関わる看護のことです。
創傷では、褥瘡対策委員会の一員として院内の褥瘡発生予防のための啓蒙活動を行い、 褥瘡を持つ患者さんには様々な職種で構成された褥瘡対策チームで院内ラウンドを行い、褥瘡の早期治癒に努めています。
ストーマでは、手術を受ける患者さんに、術前はストーマの説明、術後はセルフケアや日常生活指導、退院後は日常生活上のトラブルへの対応など、 入院前~社会復帰後までサポートしています。
失禁では、尿や便失禁により生じたスキントラブルへのケアを行っています。
患者さんがその人らしく生活できるように、スキンケアや排泄ケアを通してサポートしています。お気軽にご相談ください。
|
緩和ケア認定看護師 師長代理 高島 留美 |
「緩和ケア」とは、病気と診断された時から、その病気に伴う心と身体の苦痛を和らげて「その人らしい生き方を支える」ことです。 例えば、今食べたいものや、今やりたいこと、家族に囲まれて過ごしたい、自然な形で最期を迎えたい、といったお一人おひとりの心の声を大切にしています。 そして私は、その心の声を叶えられるように「苦痛を和らげる看護」を提案できる認定看護師になりたいと思っています。 また、患者さんの価値観・人生の目標に関する望みを医療者も理解し、患者さん・医療者が互いに共有し合える事を目指し、 チームで協働してACPを行えるよう委員会活動も行っています。
緩和ケアチームにおける活動では、患者さんが抱える苦痛によって公認心理士や管理栄養士、薬剤師、鍼灸師、リハビリ専門士など、 各専門職に積極的に繋げています。その他、看護外来ではリンパ浮腫セラピストとして、圧迫療法の指導やドレナージを実施しています。 そして聞き書き水曜会におけるサークル活動では、希望される患者さんに「聞き書き」を行うなど、幅広く活動しております。
今後は、患者さんのもつ様々な苦しみを少しでも理解し、さらにその方の尊厳を高められよう日々努力していく所存です。どうぞよろしくお願いします。
|
緩和ケア認定看護師 碓井 未央 |
みなさんは緩和ケアという言葉にどのような印象をお持ちでしょうか。「人生の最期」「もう治療ができない」などというネガティブな印象でしょうか。 緩和ケアは、がんと診断された時から始まります。医師や認定看護師をはじめ様々な職種が関わることで、身体や心のつらい症状を和らげ、 その人らしく日常生活を送ることができるよう支援しています。また、ご自宅など希望する療養場所へ戻るために、 患者さんご自身が症状と上手に付き合えるような援助や、療養環境を整える援助も行っています。 私は、患者さん・ご家族の価値観を大切にし、みなさまの希望する療養場所で、希望する過ごし方をしていただきたいと考えています。 そのため、認定看護師として自己研鑽を積み、日々邁進していきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
|
がん化学療法看護 師長代理 山田 裕子 |
私は、外来化学療法室で看護実践を積むと共に、当院のがん化学療法看護の標準化や質の向上を図るため、 院内活動を行っています。
化学療法室では、患者さんの抗がん剤治療中の安全を確保すると共に、ご自宅で起こりうる副作用に患者さん自身や ご家族が対応でき、安心して過ごすことができるように身体・精神・社会面からの支援を行っています。
院内では、当院の看護師が、患者さんやご家族にがん化学療法看護の高度な知識や技術を提供できるように、 定期的に研修会を行っています。
がん治療は、患者さんやご家族を中心としたチーム医療であると言われています。医師・看護師・薬剤師・事務など 様々な職種が効果的に連携・協力し合うことで、患者さんやご家族にがん治療の最大限のメリットが提供されるよう、日々努力しています。 どうぞ、お気軽にお声を掛けて下さい。
|
がん性疼痛認定看護師 主任看護師 前田 真裕美 |
がん性疼痛とは、がん患者さんの体や心の痛みのことをいいます。痛みを我慢すると、睡眠や食欲または活動に大きな影響を及ぼし、 日常生活に支障をきたします。そのため、痛みを抱えているがん患者さんが早い段階で痛みから解放され、 その人らしい生活が送れることを目標に看護ケアをしています。
がん性疼痛看護認定看護師は、がん患者さんの痛みの原因などを考え、その痛みが和らぐ方法を導き出すこと、 がん患者さんの痛みに対する薬剤の適切な使用と管理およびその効果や副作用を評価すること、 薬物療法だけでなくマッサージや温罨法などの非薬物療法によるケア方法を検討していくことが大きな役割となっています。
私は現在、緩和ケア病床に勤務しています。医師や専門知識をもったスタッフと一緒に、痛みをはじめとした苦痛を和らげるケアをさせていただいています。 患者さんや家族が苦痛から解放され、その人らしく充実した毎日を過ごすことができるお手伝いをしていきたいと考えています。 どうぞよろしくお願いいたします。
|
感染管理認定看護師 看護部科長、感染対策室 室長 村本 由子 |
2010年4月より感染対策室に専任で配属され、安心で安全な医療を皆さんに提供できるように日々活動を行っています。
・「1処置2手洗い」など感染対策の基本である標準予防策実践のための継続した啓蒙と教育
・手術部位感染サーベイランス(結腸手術)の実施
・病院感染発生時の対応
・感染マニュアルの整備と教育
・厚生センターなど外部機関への情報提供
などを行っています。また、病院感染の原因となる耐性菌が検出された場合や感染制御が困難な事例に対して
ICT(感染制御チーム)の一員としてICTラウンドを行っています。スタッフと共に患者さんにあった感染拡大防止対策を立案し、
病院内だけでなく在宅や施設でも安心した医療を継続いただけるように関わっています。
砺波医療圏の第二種感染症指定医療機関として、また感染対策向上加算1医療機関として地域の高齢介護社会福祉施設、クリニック等への訪問、 手指衛生、個人防護服の着脱など感染対策の指導、支援を行っています。
|
感染管理認定看護師 高松 広彰 |
2022年より感染管理認定看護師として勤務しています。
感染管理というと昨今は新型コロナウイルス感染症の対策に目が行きがちですが、入院中の医療器具の管理や患者さんのベッド周囲の環境、 手術後の管理など、さまざまな面で感染対策を実践していくことが重要です。
また、感染対策はひとりで行うものではなく、現場で働くスタッフ全員で継続して行うことが求められます。 患者さん、そして現場のスタッフが感染の脅威から守られ、安全な医療が提供されるよう、感染対策の実践を支援する活動を行っています。
|
手術看護認定看護師 師長代理 越塚 奈美 |
手術看護認定看護師の役割は、患者さんの手術侵襲が最小限になり、二次的合併症を予防し術後の回復過程を促進するよう、 術中の看護実践を行うことです。
手術という身体に負担の大きい治療の場では、患者さんの身体に様々な問題が起こることが想定されます。 それらの合併症を防止するための計画を立て、手術による創傷以外の傷を患者さんに負わせることなく、安全に手術を終えてもらう為の看護を 自らが実践することに加え、スタッフに対しての指導を行っています。
手術を受けられる患者さんが、入院から退院までの間、安全に安心して過ごしていただけるような看護が 提供されることを目標に、外来・病棟看護師、他分野の認定看護師と連携を充実させていきたいと思います。
|
乳がん看護認定看護師 主任看護師 高畠 梨絵 |
乳がんにかかる患者さんは年々増加しています。患者さんの多くは30代~60代の子育て世代や働き盛りであったりします。 また、乳がんの治療は、化学療法、手術療法、ホルモン療法、放射線療法など、様々な方法で行われています。 私は患者さんが家庭や仕事と両立しながら、納得して治療を受けられるように一緒に考え、サポートしたいと思っています。 どうぞ気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。
修了した特定行為区分
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連・創部ドレーン管理関連
|
摂食・嚥下障害看護 科長 田中 晴美 |
「口から食べること」は、多くの患者さんやご家族が望まれています。 その思いに応えられるようお一人でも多くの患者さんが安全に口から食べることができ、 食べる喜びを感じていただけるよう摂食嚥下障害対策委員会での活動を通じてサポートしていきます。
|
摂食・嚥下障害看護 主任看護師 谷口 めぐみ |
「衣・食・住」とは人が生活するうえでの基本となり、欠かせないものといえます。 その中で、「食」は第一に生命維持に必要であり、また人との絆を深め、その人がその人らしくいきいきと生活することができる活動の一つだと考えています。
私は病気や手術、環境の変化などの影響により口から食事がとれなくなった患者さん、自分で食べることが難しいと感じておられる患者さんと 関わる機会が多くあります。当院は医師、歯科医師、看護師、リハビリスタッフ、歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師などの多職種でチームを作り、 口から食べることに問題のある患者さんに安全に食事摂取していただくことを目標に活動しています。
一人でも多くの患者さん、ご家族の「口から食べたい」の思いに寄り添い、口から食べる喜びを感じ、 いきいきと生活していただけるよう支援させていただいきたいと思っています。どんなささいなことでも質問や相談をお受けいたします。 お気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。
|
摂食・嚥下障害看護 主任看護師 安田 賢治 |
私は『食べること』を支える看護師です。
食事の時に咳が出る鼻水が出る、液体でむせる、食べ物がのどに引っかかるなど、食べることに悩みを抱える患者さんの問題はさまざまです。
多職種で協力して、食べることに悩みを抱える患者さんの「口から食べたい」思いに応え、ご家族の「口から食べてもらいたい」思いを支え、
お手伝いさせていただきます。
修了した特定行為区分
・栄養および水分管理に係る薬剤投与関連
|
認知症看護認定看護師 師長代理 畑 真夕美 |
近年、認知症を抱えながら治療を受ける患者さんは増えてきています。
認知症患者さんは、自分の思いを上手く表現できないために、周囲の人が認知症患者さんの気持ちをくみ取る事は難しいです。 そのため自分がいまどこにいるのかなど場所がわからないや、誰に助けを求めたらいいのかわからない、 またさっきまでの自分が何をしていたのか思い出せないことがありとても不安をいだいています。 患者さんの不安を少なくし今まで通りいきいきと生活することができるように支援することを心がけていきたいと思います。
認知症患者さんは治療や検査を受ける時に不安になり最後まで治療や検査を受ける事が出来ない事があります。 認知症患者さんに対し、治療や検査について1つ1つ説明し、不安や苦痛をできるだけ最小限にして治療や検査を受けることができるように 関わっていきたいと思います。また認知症患者さんとご家族を中心に、医師・看護師・薬剤師・リハビリスタッフなど様々な職種と連携をとりながら、 認知症患者さんの人としての誇りを尊重したチーム医療を行っていきたいと考えています。これからも、患者さんとご家族の出会いを大切にし、 患者さんのいだいている思いや不安をうかがいながら、その思いを代弁できる看護師でありたいです。気楽に声をおかけ下さい。
|
脳卒中看護認定看護師 主任看護師 池守 実智代 |
「脳卒中」とは、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、脳の血管が破綻する「脳出血」、脳の血管に出来た動脈瘤が破裂する「くも膜下出血」をさします。 いずれも突然発症することが多く、時には重篤な意識障害や腕や足の麻痺といった機能障害を残してしまうことがあります。
脳卒中看護認定看護師の役割は、脳卒中を予防するための啓発活動、発症初期から症状の重篤化の回避、 回復期での生活の再構築に向けた支援、脳卒中の再発予防(血圧測定の仕方、生活指導)などが上げられます。 脳卒中発症後、患者さんやご家族の生活が一変し、長期間のリハビリが必要となることが少なくありません。 そのため、医師、看護師、リハビリスタッフ、医療ソウシャルワーカーなど、多職種を交えたチームで患者さんを支えていきます。 様々な機能障害を抱えながらの日常の生活動作(喋る、食べる、歩く、トイレに行くことなど)全てがリハビリになります。 脳卒中看護認定看護師は、患者さん自身の持てる力を引き出し、患者さんやご家族の願いや思いに寄り添い、 その人がその人らしい生活を送れるように支援して行きたいと思っております。心配にことやご不明な点がございましたら、 いつでもお気軽にお声をかけてください。よろしくお願いします。
|
呼吸器疾患看護 師長代理 岸澤 由紀子 |
呼吸器疾患看護認定看護師として、呼吸障害を来たした患者さんの重症化予防や症状の緩和、酸素や人工呼吸器管理、
在宅で生活する上での支援などを行っています。また、特定行為では人工呼吸器の設定の変更や動脈から採血を行い、
人工呼吸器からの早期の離脱を目標に活動を行っています。
特定行為とは、診療の補助であって、看護師が手順書(事前の指示)により医師の指示を待たずに一定の行為を行うことが可能となり、
患者さんの状態にタイムリーに対応できます。特定行為は病院だけでなく、在宅で療養する患者さんにもタイムリーに
治療を受けられるようにできた制度です。
病院だけでなく、在宅で酸素療法や人工呼吸器の治療を受けながら生活をされている呼吸器の病気の患者さんは増加しています。
患者さんの一番身近な医療者として、看護ケアを提供し必要であれば特定行為を実践し、 病院・在宅を問わずトータルで患者さんを支えられるように努めていきたいと思っています。
修了した特定行為区分
呼吸器(気道確保に係るもの)関連
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
動脈血ガス分析関連
栄養および水分管理に係る薬剤投与関連
|
クリティカルケア 森田 高彰 |
私は2023年にクリティカルケア認定看護師の資格を取得しました。
クリティカルケアとは、主に救急外来や集中治療室で行われる看護のことです。救急外来では、救急車で搬送された患者さんや 直接来院された患者さんに対して、症状などを踏まえて診察の優先順位を判断するトリアージを行い、医師の診察や処置がスムーズに進むよう 調整しています。また集中治療室では、治療を受けている患者さんの病気や怪我が重篤化しないよう医師を含めた多職種と協働し早期回復を支援しています。
私は、クリティカルケア認定看護師として、患者さんの生活状況などを聞きながら、緊急性の高い状態や重篤な状態を脱し、可能な限り元の生活に 戻れるよう看護を行っていきたいと考えています。また、患者さんだけでなく、ご家族など患者さんを取り巻く周囲の方々の不安を軽減 できるよう支援していきたいと思います。
|
がん放射線療法看護 臺蔵 由紀子 |
放射線療法は手術や薬物療法と並ぶがんの3大療法の1つです。放射線療法はからだを傷つけることなくがんの部分に放射線をあてて治療します。 からだへの負担が少ないため、ご年配の方や手術、薬物療法が難しい方でも治療を受けることができます。
私は患者さんやご家族が安心して放射線療法を受けられるように気がかりになっていることがないかお聴きし、必要な情報を提供しながら 不安を軽減できるように努めます。また放射線療法による副作用が見られた場合は患者さんに適切なケアを提供し、その人らしく生活しながら 予定された治療をやり遂げられるように支援していきます。
修了した特定区分
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
|
特定行為看護師 主任看護師 八田 枝美 |
特定看護師という看護師をご存知でしょうか?特定看護師とは、急性期から在宅医療など様々な現場で、 患者さんの病状が変化した時に看護ケアだけでなく、医師の指示を待たずに予め医師と申し合わせた手順書に沿って必要な医療行為の一部を 行うことができる看護師です。
2020年3月に特定行為研修を修了し、現在は集中治療室を中心に活動を行っています。 人工呼吸器を付けていらっしゃる患者さんの看護ケアにあたりながら、必要なタイミングで手順書のもと人工呼吸器の調整を行ったり、 気管カニューレの交換を行ったりしています。また、医師や呼吸理学療法士とともに、呼吸器ケアチームの一員として、 入院中の患者さんの呼吸器に関わる治療や看護ケアをチームで支える活動をしています。
入院中の患者さんや在宅療養中の患者さんに、特定行為を活用して、安全でタイムリー(必要なタイミング)なワンランク上の看護ケアを 提供していきたいと思っています。
*修了した特定行為区分
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
・呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
・栄養および水分管理に係る薬剤投与関連
|
特定看護師 主任看護師 鍋田 里子 |
私は、訪問看護ステーションに所属し、2021年3月に創傷管理関連の区分で特定行為研修を修了しました。 医師がすぐに駆けつけることができない在宅の環境で、事前に申し合わせた手順書に沿って、必要なタイミングでの点滴、創傷管理を行っています。
院内だけでなく、地域の多職種の方々とも連携し、病気や障害、年齢を問わず地域の皆さまが住み慣れた自宅で安心して生活できるよう支援しています。 いつでもお気軽にご相談ください。
修了した特定行為区分
・創傷管理区分
・栄養および水分管理に係る薬剤投与関連
|
特定看護師 大笹 里菜 |
私は2024年3月に特定行為研修を終了し、高度治療室・救急を中心に活動しています。
人工呼吸器装着中の患者さんや呼吸や循環など全身状態が不安定な患者さんに対して、手順書を用いて必要なタイミングでタイムリーに 動脈血採血を行い、全身状態を把握した上で人工呼吸器の設定変更を行っています。また、てんかん発作のある患者さんに対しては、早期に てんかん発作が消失するよう薬剤投与を行っています。
患者さんの側に寄り添いながら、『治療』と『生活』の両面から支援を行い、患者さんの立場に立ったケアを提供していきたいと思っています。
修了した特定行為区分
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
・動脈血液ガス分析関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・精神および神経症状に係る薬剤投与関連
電話でのお問い合わせ
![]() 0763-32-3320
0763-32-3320



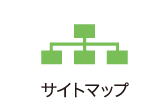


 外来担当一覧(PDF)
外来担当一覧(PDF)